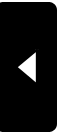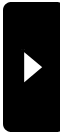2011年09月30日
はじめての宗教論 右巻 ー第4章 キリスト教と国家ー
第4章 キリスト教と国家-啓示とは何か?
<目次>
ポルターガイスト騒ぎ
ユダヤ教への改宗
キリスト教の創設者は誰か?
教会本来の運営原則
石打刑のしきたり
啓示の本質
使徒たちの内ゲバ
聖書の行間を読む
なぜ「イエス・キリストの名」なのか
固有名詞という問題
パウロの人間力
ギリシャ哲学の3つの派
貨幣もまた偶像である
「肉体」をめぐるすれ違い
税金は絶対に払え!
終末の到来
黙示録の革命的要素
悪の数字666
<要約>
ポルターガイスト騒ぎ
キリスト教の成り立ちを聖書に即してみていく。
使徒言行録に
「五旬祭がきて、使途が一堂に会していると、突然、激しい風が吹いて、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、ひとりひとりの上にとどまり、‘霊‘に満たされ、他の国々の言葉で話し出した」
とある。この「突然激しい風が吹いて」との記載がある。
これはプネウマのことである。霊が来て、ポルターガイストのようにガタガタと家を揺らす。
また「炎のような舌が分かれ分かれに現れ、ひとりひとりの上にとどまった」とある。
これは言葉のことである。
つまり、みな、酒を飲んで相当出来上がっているところに、聖霊が現れて、扉をがんがんたたいて、炎のようにワーッと喋り始めた。これが教会誕生のときで、外部からは酔っ払いの集団のように見えた。
キリスト教の創設者は誰か?
教祖はイエス、開祖はパウロである。
教会本来の運営原則
本来は持っているものをみなでわかつ。150人くらいの顔が見える範囲での共産主義的な生活であった。
外の世界でいやな目にあっても、この教会の中ではみながイエスの教えに従うし、金がなくても食っていける、地上における神の国とした。
石打刑のしきたり
啓示の本質
使徒たちの内ゲバ
聖書の行間を読む
最初の殉教者ステファノが出る。彼は石打ちという残酷な刑罰でなくなった。
そのステファノの殺害に賛同したサウロという悪いヤツがいた。
彼はキリスト教の迫害にたいそう熱心であったが、突如天から光が降りてきて、サウロは地に倒れる。
その後、キリスト教のアナニアがたずねてきて、あの光はイエスからの啓示だったとつげた。サウロはパウロに改名し、キリスト教の開祖となった。その後、ギリシャ語を喋るユダヤ人、非ユダヤ人にキリスト教は広がったが、エルサレムにいるペテロたちとぶつかるようになった。
ペテロたちの主張は「革命のためにはまずプロレタリア的な等をきちんと作って、思想的・組織的・運動的にユダヤ教の連中ののりこえを実現する。そのような形で革命に備えるべきだ。」
パウロたちの主張は「この世の終わりはもう近い。だから一刻も早くないランを革命に添加せよ、そのためには今までの経緯にこだわらずどんな連中であれ仲間に入れて強化したほうがよい」。
最終的な救済という目的は同じだが、戦略に差が出る。
現在はペテロの系統は途絶え、パウロの系統が残るのみである。
なぜ「イエス・キリストの名」なのか
固有名詞という問題
プロテスタントは最後に「主イエス・キリストの御名において」ととなえ、カトリックは「父と子と聖霊の御名において」ととなえる。どちらにせよ誰かの名前を通して、神との取次ぎを頼まないといけない。
律法を遵守してトーラーを読み、そのとおりに行動している天でイエスの信者たちはパリサイと変わらない。しかし、イエスの名によって神に救ってもらおうとしているところが決定的な違いである。
パウロの人間力
ギリシャ哲学の3つの派
貨幣もまた偶像である
「肉体」をめぐるすれ違い
税金は絶対に払え!
パウロは頭もよく、ユーモアがあり非常に人をひきつける要素があった。
しかし、パウロの説くキリスト教は当時のヘレニズムの知的世界ではナンセンスであった。
当時のギリシャにはエピクロス派(知的な快楽を求める)、ストア派(禁欲)、キニク派(シニカルで何も求めない)があった。しかし「肉体は魂にとっての牢獄だ」という考え方が当時のローマでは一般的で、いずれの派もパウロの説く「死者の復活」は受け入れがたかった。そのため、パウロが外国の新しい神を宣伝しにきたと考えていた。
一方のパウロも当時のアテネでみなが偶像を拝んでいるのを見て驚いている。
当時のアテネは文化の爛熟期を過ぎて衰退が始まっていた。退屈していた人々のもとにパウロは飛び込んでいって、大演説を始める。
パウロはが身が一人の人間からあらゆる民族を作り、地上のいたるところに住まわせ、季節を決め、居住地の境界を決めた、と述べた。
大切なのは境界で、みなそれぞれ自分の領域でがんばりなさいといった。
パウロは税金は必ず払え、為政者は尊敬しろと畳み掛ける。
その上で、偶像崇拝を戒めた。
パウロの伝道はおおむね成功したがアテネでは失敗した。なぜなら先ほど述べたように肉体をめぐるすれ違いがあったからである。
終末の到来
黙示録の革命的要素
悪の数字666
同じ聖書でも国家に批判的な場合はヨハネの黙示録を参照し、親体制的な場合はローマの信徒への手紙を参照する。
その、ヨハネの黙示録では延々と終末期の様子がつづられる。
イエスの弟子たちは近未来にこの世の終わりが来ると考え、イエスの言説について書き残すよりも早く改心して、この世の終わりに備えよ、というイエスの教えを広めることに尽力した。
しかし、週末はいまでたってもきていない(終末遅延の問題)。
こうして地上はだんだん混乱してくる。するとその混乱を収めるために強い国家、強い権力者が現れるが、ここでは『獣』と表彰され、国家への忌避が感じられる。
ヨハネの黙示録13章には「二匹の獣」の記述がある。
「獣」の背後にはサタン、竜が着いている。国家の背景には悪魔がいる。この「獣」には<大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられた>とある。だから国家は「美しい国」とか「毅然たる政策を遂行する」と大言を吐く。そしてこのような国家を拝む人間は偶像崇拝に当たるため、絶対に救われないと明言されている。
黙示録は地上の権力を認めない、革命的な姿勢が強く打ち出され為政者から忌避されることが多い。
では、国家にはどのように抵抗すればよいのか?
それは圧倒的な権力に対して革命を起こして理想的な社会を作ることではなく信仰を維持すること。そうすれば向こう側から、神のほうから救済が来る(千年王国)とされている。しかし、その後に第二の国家がやってくる。(666はキリスト教徒を迫害した暴君ネロの数字)。 黙示録でもっとも大事なのは竜で表彰される国家の外部性である。
キリスト行為とって聖書とは人間の知恵によって作られたものではなく、外部からの強烈な啓示が人間に降ってきた結果出来上がったもの。
キリスト教徒にとって重要なのは国家ではなく個人の救済であり、それは啓示により完成する。そして、啓示は人間の実存の外、すなわち外部から突然やってくる。
タグ :佐藤 優
ヨン様やヅカにハマる人、ハマらない人。
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その2-
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その1-
はじめての宗教論 左巻 -第2章 宗教とナショナリズム-
はじめての宗教論 左巻-第1章 近代とキリスト教-
はじめての宗教論 左巻 -序章-
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その2-
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その1-
はじめての宗教論 左巻 -第2章 宗教とナショナリズム-
はじめての宗教論 左巻-第1章 近代とキリスト教-
はじめての宗教論 左巻 -序章-
Posted by キミドリ at 07:00│Comments(0)
│10分くらいで読んだ気になれる、かも。