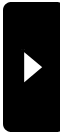2010年05月31日
パンを焼いてみた。2
図書館でも色々な本がありました。
あるていどアマゾンをみながら当たりをつけていたけど、それでも迷うくらい(^^;)
何冊か借りてきたけど、今回はこの本のレシピを参考にすることに。
選んだ理由は、
・ホームベーカリーでの作り方がのっている(我が家にホームベーカリーがあるため)
・天然酵母で焼き比べている(ホシノ天然酵母、白神こだま酵母、ベターホーム天然酵母、生イースト、パネトーネマザー)
の2点。
この本を参考にし、比較的イーストに近く失敗が少ないと思われた、白神こだま酵母を使用しました。

これは楽天の「ケンコーコム」さんで購入。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/kenkocom/
レシピはこのとおり。

で、ホームベーカリーに材料を投入し、待つこと4時間で・・・
 完成です!!(チューボーですよ風に)
完成です!!(チューボーですよ風に)

翌日、ピーナツバターをつけて朝食にいただきました。
だいぶレシピがバターリッチだったので、バターの香りがします。
おいしい
ただ、ふわっとしたカンジが強くて、イーストの出来と違いがあまりわかりませんでした
ちなみに、ウチのホームベーカリー。パナソニック製。
ホームベーカリーが出始めたころの製品で、軽く、10年以上経ってるよ??でも、いまだに現役。

最新のホームベーカリーはうどんやジャムもできるらしいです
でも、いまのところ、そういうのは求めていないのでこいつで充分www
しかし、ひとつ問題があるとすれば、最初の捏ねるとき、ガッチャンガッチャンとすごい音がする。
最新の機種はもっと静かなんだろうか・・・???
でも、メーカーが掃除機みたいに「静かです!」と謳っていないところをみるとあまり変わってないのかもしれない
あるていどアマゾンをみながら当たりをつけていたけど、それでも迷うくらい(^^;)
何冊か借りてきたけど、今回はこの本のレシピを参考にすることに。
選んだ理由は、
・ホームベーカリーでの作り方がのっている(我が家にホームベーカリーがあるため)
・天然酵母で焼き比べている(ホシノ天然酵母、白神こだま酵母、ベターホーム天然酵母、生イースト、パネトーネマザー)
の2点。
この本を参考にし、比較的イーストに近く失敗が少ないと思われた、白神こだま酵母を使用しました。

これは楽天の「ケンコーコム」さんで購入。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/kenkocom/
レシピはこのとおり。

で、ホームベーカリーに材料を投入し、待つこと4時間で・・・
 完成です!!(チューボーですよ風に)
完成です!!(チューボーですよ風に)
翌日、ピーナツバターをつけて朝食にいただきました。
だいぶレシピがバターリッチだったので、バターの香りがします。
おいしい

ただ、ふわっとしたカンジが強くて、イーストの出来と違いがあまりわかりませんでした

ちなみに、ウチのホームベーカリー。パナソニック製。
ホームベーカリーが出始めたころの製品で、軽く、10年以上経ってるよ??でも、いまだに現役。

最新のホームベーカリーはうどんやジャムもできるらしいです

でも、いまのところ、そういうのは求めていないのでこいつで充分www
しかし、ひとつ問題があるとすれば、最初の捏ねるとき、ガッチャンガッチャンとすごい音がする。
最新の機種はもっと静かなんだろうか・・・???
でも、メーカーが掃除機みたいに「静かです!」と謳っていないところをみるとあまり変わってないのかもしれない

2010年05月30日
パンを焼いてみた。1
先月、酵母パン教室に行って以来、自宅でもひそかに酵母パンを作りたい、という野心を燃やしていた私(笑)。
昨日、ようやっと成就しました。
まずは、「天然酵母」とはなんぞや?
はてなきーわーどより。
「酵母のうち単一の株を培養されたものではなく、果実や穀物、空気中に含まれているもの。」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%C1%B3%B9%DA%CA%EC
「天然」、があれば対立する「人工」があるわけですが、これは市販の製菓材料売り場でよく目にする「ドライイースト」です。これも「酵母」には違いないのですがアルコールなどが添加されています。
その市販のイーストの化学物質くささを敬遠して、天然酵母にこだわるヒトが多いらしい。
で、この「天然酵母」と「市販のドライイースト(人工酵母)」ですがそれぞれメリット、デメリットがあります。
天然酵母のメリットは、市販のものでは味わえない「風味」。先のはてなキーワードでも引っ張ってきましたが、単一の菌じゃないので、味わいが複雑になります。
しかし、最大のネックは発酵時間が天候に左右され、時間が読めないこと。
さて、天然酵母、の代表格といえば星野天然酵母です。
使いやすくて風味があるのですが、先の時間のネックを克服したことが勝因のようです。
逆に「市販のイースト」は発酵力が強いです。
なので、そのときの天候に左右されずに発酵させたい時間にきちっと仕事をしてくれる。
デメリットは先にあげたとおりです。
今は天然酵母が花盛りですが、そんな天然酵母にも色々種類があります。
先にあげた星野酵母、あこ酵母・・・。
あとは自分でレーズンやヨーグルトから起こしたものまで。
で、勉強がてら、天然酵母のパンの本を図書館で借りれるだけかりてきました。
つづく。
昨日、ようやっと成就しました。
まずは、「天然酵母」とはなんぞや?
はてなきーわーどより。
「酵母のうち単一の株を培養されたものではなく、果実や穀物、空気中に含まれているもの。」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%C1%B3%B9%DA%CA%EC
「天然」、があれば対立する「人工」があるわけですが、これは市販の製菓材料売り場でよく目にする「ドライイースト」です。これも「酵母」には違いないのですがアルコールなどが添加されています。
その市販のイーストの化学物質くささを敬遠して、天然酵母にこだわるヒトが多いらしい。
で、この「天然酵母」と「市販のドライイースト(人工酵母)」ですがそれぞれメリット、デメリットがあります。
天然酵母のメリットは、市販のものでは味わえない「風味」。先のはてなキーワードでも引っ張ってきましたが、単一の菌じゃないので、味わいが複雑になります。
しかし、最大のネックは発酵時間が天候に左右され、時間が読めないこと。
さて、天然酵母、の代表格といえば星野天然酵母です。
使いやすくて風味があるのですが、先の時間のネックを克服したことが勝因のようです。
逆に「市販のイースト」は発酵力が強いです。
なので、そのときの天候に左右されずに発酵させたい時間にきちっと仕事をしてくれる。
デメリットは先にあげたとおりです。
今は天然酵母が花盛りですが、そんな天然酵母にも色々種類があります。
先にあげた星野酵母、あこ酵母・・・。
あとは自分でレーズンやヨーグルトから起こしたものまで。
で、勉強がてら、天然酵母のパンの本を図書館で借りれるだけかりてきました。
つづく。
2010年05月29日
「エッセイ脳」【読書】
はっ、と気が付くと7万プレビューを越えていました。
いつもお越しいただき、ありがとうございます。
最近はより読みやすいブログを目指して、文章術を研究中ですwww
まー、ブログ一般ってカテゴリーとしては「エッセイ」にはいるのかな?と、思い、下記を衝動買い(笑)
岸本葉子「エッセイ脳」
私はこの方のエッセイと知って読んだことがありません。
が、流麗な文体といい、ユニークさを保ちつつかつ上品さを漂わせている文章であることから、現代文の教科書などで、無意識のうちに目にしている可能性は大です。
昨日と同じく、内容を独断と偏見の上で3つの点に絞り、解説していきます。
1. A「自分の書きたいこと」をB「他人が読みたくなるように」書く。
しかし、Aばっかり重視しても読むほうはしんどくなるか、めんどくさくなるだけなので(笑)、
A<Bだと著者はいっています。
たしかにひとりよがりなグチばっかりの文章じゃ読む気なくなるしwww
2.考えるときは「転」からはじめる。
これは昨日の齋藤先生に同じですね。
http://kimidori608.shiga-saku.net/e442609.html
この方は「テーマ」を与えられてからエッセイを書くことが多いですが、その「テーマ」から予想される出来事を予想されるように書いたのでは面白くない。
独自の視点から見て、読者の予想を裏切り「へぇ~っ」と思わせるのがミソ。
3.文章には「3種類」ある。
A 枠組みの文:状況の説明。
B 描写:具体的に書き込む。
C 会話:はなしことば。便利だけど、多用すると文章にしまりがなくなるので注意。
の3つで構成されているそうです。
それぞれがどのような役割かを自身のエッセイを用いて解説されています。
特に思わず唸ったのが3番目でした。
ところで、「私の文章が男に間違われる」と以前書いたことがあります。
「ル・ゴーシュ・セキにて。9~おあとがよろしいようで。~」
http://kimidori608.shiga-saku.net/e442609.html
上の分類で行くと、私の文章は圧倒的に「A 枠組みの文:状況の説明。」が多いように思います。
女性のブロガーさんによくある「自分がああ思った、こう思った」というのを直截にくどくど書かない。
「感情の記載が少ない」ようです。そう考えると極端に形容詞を用いてないかも。
私から言わせると「おいしい」や「きれい」と感じたから記事にしているわけでなんでわざわざそれをくどくどいわなあかんの??となってしまうわけです。
ま、それはそれで情緒のない意見のような気もしますが・・・
いつもお越しいただき、ありがとうございます。
最近はより読みやすいブログを目指して、文章術を研究中ですwww
まー、ブログ一般ってカテゴリーとしては「エッセイ」にはいるのかな?と、思い、下記を衝動買い(笑)
岸本葉子「エッセイ脳」
私はこの方のエッセイと知って読んだことがありません。
が、流麗な文体といい、ユニークさを保ちつつかつ上品さを漂わせている文章であることから、現代文の教科書などで、無意識のうちに目にしている可能性は大です。
昨日と同じく、内容を独断と偏見の上で3つの点に絞り、解説していきます。
1. A「自分の書きたいこと」をB「他人が読みたくなるように」書く。
しかし、Aばっかり重視しても読むほうはしんどくなるか、めんどくさくなるだけなので(笑)、
A<Bだと著者はいっています。
たしかにひとりよがりなグチばっかりの文章じゃ読む気なくなるしwww
2.考えるときは「転」からはじめる。
これは昨日の齋藤先生に同じですね。
http://kimidori608.shiga-saku.net/e442609.html
この方は「テーマ」を与えられてからエッセイを書くことが多いですが、その「テーマ」から予想される出来事を予想されるように書いたのでは面白くない。
独自の視点から見て、読者の予想を裏切り「へぇ~っ」と思わせるのがミソ。
3.文章には「3種類」ある。
A 枠組みの文:状況の説明。
B 描写:具体的に書き込む。
C 会話:はなしことば。便利だけど、多用すると文章にしまりがなくなるので注意。
の3つで構成されているそうです。
それぞれがどのような役割かを自身のエッセイを用いて解説されています。
特に思わず唸ったのが3番目でした。
ところで、「私の文章が男に間違われる」と以前書いたことがあります。
「ル・ゴーシュ・セキにて。9~おあとがよろしいようで。~」
http://kimidori608.shiga-saku.net/e442609.html
上の分類で行くと、私の文章は圧倒的に「A 枠組みの文:状況の説明。」が多いように思います。
女性のブロガーさんによくある「自分がああ思った、こう思った」というのを直截にくどくど書かない。
「感情の記載が少ない」ようです。そう考えると極端に形容詞を用いてないかも。
私から言わせると「おいしい」や「きれい」と感じたから記事にしているわけでなんでわざわざそれをくどくどいわなあかんの??となってしまうわけです。
ま、それはそれで情緒のない意見のような気もしますが・・・
2010年05月28日
原稿用紙10枚を書く力【読書】
きのうは「文章術」について触れました。
そんなに冊数は読んでいないですが、その上でよみくらべた感想は、
「文章術って人それぞれ。」
・・・。
・・・。
・・・。
しかし、その結論で帰結してしまっては学ぶ余地がない。
「誰でも書ける!」とは言わなくてもいいけれど、練習すれば長い文章も書けるし、その実践的な方法が書いてあればよりベターです。
その点で、この本は私が知る限りいちばん「実践的」な本でした。
著者の齋藤先生は「声に出して読みたい日本語」が大ベストセラーとなりました。
が、私個人としては一番お世話になっているのはこの本です。
その中でのポイントとしては、以下の3点です。
1.論文、評論、エッセイ、小説などのカテゴリーにこだわらず10枚書く!
2.ハナシは「転」から考える!
3.「3つ」の法則を活用する!
まず、1論文、評論、エッセイ、小説などのカテゴリーにこだわらず10枚書く!。
齋藤先生によると、10枚書く、というのはひとつの分水嶺だそうな。
これができるのはそれなりに「文章力」のあるヒトである。
しかし、イキナリは難しい。まずは、引用を使って書くなどの「トレーニング」が必要、だそうです。
つぎに、2.ハナシは「転」から考える!
これは私にはすんなり入ってきやすかったです。
先生の言う「転」は「フツーならこういくと思っていたのがハズれる」、つまり、よい意味で裏切られる場面だったりします。
そういう定義で行くと、私の「書こう!」という気持ちが掻き立てられる瞬間はだいたい「転」ですから。
最後の3.「3つ」の法則を活用する!。
これは何かを書くときにはポイントを「3つ」あげる、ということです。先生いわく、「2つ」だと直線的になるが、「3つ」だと多様性が出てくる、とのこと。
これは本を読んだり、映画を見たりして感想を書くときにも感動した箇所を「3つ」あげさせることがオリジナリティのある読書感想文や、映画批評になるそうです。
最後の法則は私自身も多用してます。
すでにこの記事でも使っています、もうお分かりですよね??
2010年05月27日
最近考えていること。~ある意味お知らせ~【雑記】
最近、すっかり暑くなりましたね。
5月というのに30度越したり。
さて、わがブログも記事数750を越しました。単純にいうと2年強の計算ですね。
ついでに、去年の2月からほぼ毎日更新しています(1日手違いでうっかりしていたり(- -;)、旅行が挟まったりしていますが・・・)。
「スゴいコト」というより、習慣みたいなのであまり苦痛は・・・
ウソです、たまに手抜きの記事とかありましたorz
でも、最近書きたいことが増えたんですよねーーー。
正直ブログ1コじゃ足りんなーー、と。
そこで、このブログをメインのままにしておいて、ダイエット・トレーニング用ブログ、写真用ブログ、手作り用(パン、化粧品など)
をあらたに開設しようかな、と思っています。
さすがにすべてを毎日更新するのはムリなので、メインをのぞき、他のブログは週2回くらいの更新を目指しそうかなと。
複数のブログを持つことを決定してから、ネットであれやこれや調べていたんですが、最近は色々なサービスがたくさんあって迷いますねー。
自分が「どういうブログにしたいか」を決めておかないと、困る。すごく困るwww
大体のアウトラインですが、
A.メインブログ(ここです)の内容は、
・仕事に関連(もしくは考察)
・日々の雑感
・思考術
・あと「コレつくったー」「アレつくったー」などの手作り系
⇒ま、いまと基本変わりません。あ、そうそうやっぱ「滋賀ラブ」濃度をあげていく予定ですwww
B.ダイエット・トレーニング用ブログ
・レコーディングダイエットについて
・ダイエットもしくはトレーニングのための自作メニューのレポ
・マラソン大会レポ
・ランニング用音楽(おそらくはテクノ)
・筋肉トレーニング
⇒ランニング用の音楽にも力を入れていく予定なのです。ダイエット・ランニングモチベーションに必須のカウンター機能(今も横についている)も大切ね。
しかし、今までの記事の調子からして「日々の誘惑に負けずトレーニングしてます(キリッ)」てな具合にはなりそうにねーな。
C.写真用ブログは、
・写真教室のレポ
・撮影旅行or旅行時の写真
・廃墟
など。
⇒基本的には自分の写真のお勉強用ブログ。「廃墟」というマニアックかつ確固とした固定ファンがいる
領域に足を踏み込む。
同時に今まで手をつけたことのないサービス、「ウェブアルバム」にも興味あり。具体的にいうとピカサ。
本日はメモ程度の記事にお付き合いいただきありがとうございました。
また、なにかはじめたらお知らせします。
5月というのに30度越したり。
さて、わがブログも記事数750を越しました。単純にいうと2年強の計算ですね。
ついでに、去年の2月からほぼ毎日更新しています(1日手違いでうっかりしていたり(- -;)、旅行が挟まったりしていますが・・・)。
「スゴいコト」というより、習慣みたいなのであまり苦痛は・・・
ウソです、たまに手抜きの記事とかありましたorz
でも、最近書きたいことが増えたんですよねーーー。
正直ブログ1コじゃ足りんなーー、と。
そこで、このブログをメインのままにしておいて、ダイエット・トレーニング用ブログ、写真用ブログ、手作り用(パン、化粧品など)
をあらたに開設しようかな、と思っています。
さすがにすべてを毎日更新するのはムリなので、メインをのぞき、他のブログは週2回くらいの更新を目指しそうかなと。
複数のブログを持つことを決定してから、ネットであれやこれや調べていたんですが、最近は色々なサービスがたくさんあって迷いますねー。
自分が「どういうブログにしたいか」を決めておかないと、困る。すごく困るwww
大体のアウトラインですが、
A.メインブログ(ここです)の内容は、
・仕事に関連(もしくは考察)
・日々の雑感
・思考術
・あと「コレつくったー」「アレつくったー」などの手作り系
⇒ま、いまと基本変わりません。あ、そうそうやっぱ「滋賀ラブ」濃度をあげていく予定ですwww
B.ダイエット・トレーニング用ブログ
・レコーディングダイエットについて
・ダイエットもしくはトレーニングのための自作メニューのレポ
・マラソン大会レポ
・ランニング用音楽(おそらくはテクノ)
・筋肉トレーニング
⇒ランニング用の音楽にも力を入れていく予定なのです。ダイエット・ランニングモチベーションに必須のカウンター機能(今も横についている)も大切ね。
しかし、今までの記事の調子からして「日々の誘惑に負けずトレーニングしてます(キリッ)」てな具合にはなりそうにねーな。
C.写真用ブログは、
・写真教室のレポ
・撮影旅行or旅行時の写真
・廃墟
など。
⇒基本的には自分の写真のお勉強用ブログ。「廃墟」というマニアックかつ確固とした固定ファンがいる
領域に足を踏み込む。
同時に今まで手をつけたことのないサービス、「ウェブアルバム」にも興味あり。具体的にいうとピカサ。
本日はメモ程度の記事にお付き合いいただきありがとうございました。
また、なにかはじめたらお知らせします。