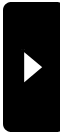2012年05月28日
「刑務所なう」読了。
先日、読み終わりました。
おもしろかったですよ。
で、思ったんですが、「ホリエモンって淋しがりなんかなー(・ω・)?」
ところでみなさんは淋しがりですか??
自分はあんまりそうじゃないな、と私は思っています。
他人と接するのが嫌いじゃないし、孤立するのは嫌だけど、「淋しがり」というのはしっくりこないなー、と。
けど、ホリエモンとか世の中に対して大きな仕事をする人って、淋しがりの人って多いんじゃないかな、と。
「大きな仕事」となると、ある程度人がたくさん集まらないとできない。
で、人が増えれば、トラブルも等比級数的に増えるし(笑)
淋しがりじゃなかったらそのへん許容できないと思うんです。
私だったら「めんどくさいしやだ」で終わりそう(笑)
タグ :刑務所なう
2012年05月15日
塀の中。
きのう、立ち読みして結局衝動買いしてしまったもの(笑)。
現在、絶賛収監中のホリエモンこと、堀江貴史氏の獄中記。
「獄中記」にありがちな悲惨さはあんまりなく、彼らしさがとっても堪能できる。w
ってもなー、本人は収監されているのに本が出せる&出そうとするっ&需要があるってスゴいょ。
働いていないと死んでしまうんだろうな、この人(笑)。
彼自身の手記も面白いですが、マンガが秀逸です。
ちゃんと、彼の手記に沿ってカリカチュアライズされている。
腕がいいんでしょう、この漫画家さん(西アズナブルってひとらしい)。
それとも、ホリエモンがマンガみたいな人だ、ということなのでしょうか??
・・・両方か。
個人的には、面会にやってきた田原総一郎が時事ネタに関してホリエモンを質問攻めにして帰っていく、というシーンが一番笑えました。wおそるべしオーバー70。
私の気に入る本は、あんまり一般受けしないのですが、コレはお勧めです。
タグ :刑務所なう
2012年05月12日
将来、ソムリエマシン、なるものが可能かもしれない。
のなかの「第7章 味覚を再現する」
より。
「(*コーヒー牛乳=麦茶+牛乳+砂糖で再現できることについて)そう、味はバーチャルなのだ。(略)その商品に含まれている化学物質を使わなくても、他の化学物質を使って同じ味を再現できるわけである。それはなぜか?
これは、味には5つの基本味が存在するからだ。食品の味をセンサーで5つの味(および渋みやコク)に分解しさえすれば、各基本味を代表する適当な化学物質を使って5つの味を、そして、食品の味を再現できる。
(略)視覚や聴覚で何気なく受け入れているバーチャルな世界、それを私たちは今や味覚で体験できるのである。」
ま、早い話、「味覚」も基本5つの要素で構成されているから、それの順列組合せを最適化できればどんな味も思いのまま、つーことです。
だから「牛乳+醤油=ウニ」とかもバカにできん、ってことです。
このセンセのHPでは「牛乳+たくあん=コーンスープ」で再現されていますね。
http://www.athome-academy.jp/archive/engineering_chemistry/0000001053_all.html
*「コーヒー牛乳=麦茶+牛乳+砂糖で再現できる」
ってことは、「麦茶」が「代替コーヒー」であった事も考えあわせると、さして珍しくはないかも、と思う。
「ドイツ人に麦茶飲ませると、『代用コーヒーの味がする』と言ってイヤがる」だそうです。
なんか、佐藤さんの本でも末期ソ連でも、「ホンモノのコーヒーを飲めるのはとってもステイタス」っていってた気がするからな。 なぜかというと、ソ連では外貨が無いためほとんどのコーヒーは大豆を炒って作った代替コーヒーだったからだそうな。
2012年04月21日
独裁国家。
よみおわりました。
面白かったー
「独裁」って最終的には皆判で着いたように同じことをやるのですが、それがいろいろわかってよかったです。
我々には滑稽に見えることが多いですが、独裁国家の必然なんだなぁ、と実感させられます。
この本の中にはジョージ・オーウェルの「1984」も取り上げられていました。
まだ、読んでないのですが…
その中で、とくに「へー」って思ったのが「ニュースピーク」。
我々のことばと比較すると、ニュースピークの語彙はわずかであり、さらにそれを削減する新たな方法が絶えず考えられていた。(略)削減するたびに利益が生まれた。というのも、選択範囲が狭まれば狭まるほど、何かを熟考しようとする誘惑が小さくなるからであ
る。/イングソック(イギリス社会主義)に有害な思想はことばを伴わない曖昧は形で心に抱くしかなくて、(略)それらを明確に定義づけないまま断罪だけする実に雑駁な用語を使うより他にないのだった。
「独裁」には言論統制が必須です。
言葉を簡略化すればするほど、平板になり、考えや信条をきめ細やかに表現することが難しくなる。
そうなると、現体制への批判を草の根レベルで根絶できる、言語統制の一環と考えた独裁者側が考えた方法、となっています。
面白かったー
「独裁」って最終的には皆判で着いたように同じことをやるのですが、それがいろいろわかってよかったです。
我々には滑稽に見えることが多いですが、独裁国家の必然なんだなぁ、と実感させられます。
この本の中にはジョージ・オーウェルの「1984」も取り上げられていました。
まだ、読んでないのですが…
その中で、とくに「へー」って思ったのが「ニュースピーク」。
我々のことばと比較すると、ニュースピークの語彙はわずかであり、さらにそれを削減する新たな方法が絶えず考えられていた。(略)削減するたびに利益が生まれた。というのも、選択範囲が狭まれば狭まるほど、何かを熟考しようとする誘惑が小さくなるからであ
る。/イングソック(イギリス社会主義)に有害な思想はことばを伴わない曖昧は形で心に抱くしかなくて、(略)それらを明確に定義づけないまま断罪だけする実に雑駁な用語を使うより他にないのだった。
「独裁」には言論統制が必須です。
言葉を簡略化すればするほど、平板になり、考えや信条をきめ細やかに表現することが難しくなる。
そうなると、現体制への批判を草の根レベルで根絶できる、言語統制の一環と考えた独裁者側が考えた方法、となっています。
タグ :ジョージ・オーウェル西川 伸一
2012年04月13日
ひさびさにアタリひいたっ!
ひさびさにアタリひいたっ!
愛してるぜ、南草津図書館!
いわずとしれた、ジョージ・オーウェルの古典的名作「動物農場」の解説。
ジョージ・オーウェルは「1984」も有名ですよね。
こっちはまだ読んでないなぁ…
愛してるぜ、南草津図書館!
いわずとしれた、ジョージ・オーウェルの古典的名作「動物農場」の解説。
ジョージ・オーウェルは「1984」も有名ですよね。
こっちはまだ読んでないなぁ…