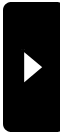2012年05月11日
ヨン様やヅカにハマる人、ハマらない人。
うちの職場にある本。
専門書の中でも、かなり異色な専門書、です。
タイトルからもわかるとおり、「依存症」に特化した雑誌です。
すっっっごく平板に言うと、「依存」というのは「愛情の代替行為」であることが多いのです。
そうなると、「愛情の生成場」である家族とは切っても切れない関係なわけです(・ω・)
だから「アディクションと家族」というタイトルです。
で、ちょっと古いですがこの号で「ヨン様や宝塚(ヅカ)にハマる、ハマらない」の話がありました。
著者は荷宮和子さん。
熱烈なヅカファンだそうです。
彼女曰く「ヅカorヨン様」にハマるのは彼女をはじめとする「団塊の世代」。
団塊Jrの世代はそれをクールに眺めている。
なぜ、ハマるハマらないに世代間格差が出るのか??
それは「恋愛・結婚・セックス」に幻想を見出せるかどうか、だそうです。
そして、世代の間に横たわる考え方の溝。
団塊の世代は「頑張れば今より、マシ。頑張らなければドツボ」。
団塊Jrの世代は「頑張るのは疲れる。頑張らなくても何とかなるし」。
だから、団塊の世代は「追い求めたら何とかなるんじゃないか」という幻想にせっつかれて「ハマる」し、それより年下はそうではない、という意見でした。
なるほどなー(・ω・)
タグ :荷宮和子アディクションと家族
2011年10月12日
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その2-
第3章キリスト教神学入門①知の全体像をつかむために
霊と魂の違い
知識を驕るな!
神学者の定義
キリスト教の職業倫理
神学者に要求される知識量とは?
才能は社会のために使え!
読書力から語学力まで
「批判」の正確なニュアンス
伝承にこだわると馬鹿になる
ダメ教会を見分ける
神学は「時代の哲学」を身にまとう
歴史は発展する―シュライエルマッハーの近代主義
すべては救済に関係づけられる
「パントブドウ酒」は何を意味するのか
実態変質説の様々な解釈
国家論としての「神学通論」
霊と魂の違い
シュライエルマッハーによると、肉体と魂は意志でつながっている。
霊と魂の違いは個性に関係するのは魂で、そうでない場合は霊である。
知識を驕るな!
神学者の定義
キリスト教への関心があるから知識がついてくる、知識がついてくるとキリスト教への関心が強まっていくと両者の弁証法的な関係があると述べる。
これはスコラ学のアムンセルス以降の弁証法的な考えである.
それをうけて、<最高度の宗教的関心と学的精神とが、しかもできる限り平衡を保って、理論と実践のために一致している場合>こそが、<教会指導者の理想的な姿である>としている。
この平衡を保つ、とは学問的訓練を受けていない大多数の一般信徒と、訓練を受けている知的能力の高いごく一部の人たちの間でバランスを取らないといけない。特に後者にむけて理屈だけで信仰の問題がわかるな、知識を驕って一般信徒をバカにしてはいけない、と説いている。
キリスト教の職業倫理
神学者になるにも牧師になるにも内的な形での召命感がないとやってはいけない。
「召命」とは特定の使命を果たすように神から呼びかけられることで、ドイツ語ではベルーフ(天職)である。
神学者に要求される知識量とは?
神学に要求される知識量は膨大であり、一生かかっても特定の分野ですら極めるのは難しい。しかし、救済につながることにはきわめて積極的に取り組む人が多く神学者は知的好奇心の強い人が多い。
才能は社会のために使え!
ひとりの神学者の卵が何を学ぶかを決めるにあたって、彼の才能はベルーフであり神から授けられたものだから、個人的な知的関心や金儲けのために使ってはいけない。社会のために使わないといけない。
読書力から語学力まで
神学者に求められる資質とは、その時代の聖書神学・歴史神学・組織神学・実践神学のそれぞれ肝となっている問題点を把握し、救済という観点からどういう意味合いを持つかを理解している。そして、それを成し遂げる手段として、読書力(ブックレビューする力)、論理学、歴史の知識、語学力が必要である。
「批判」の正確なニュアンス
批判とはよいも悪いも含めて、対象をよく吟味することである。
伝承にこだわると馬鹿になる
伝承的なことにのみ拘泥すると頭が悪くなる。学問とは、だらだら書かれていることの本質をぎゅっと縮めて提示すること。これこそが批判的な作業である。このように少しづつ厳密に詰めていくことでヨーロッパの知的な体系に近づくことができる。
根本的なことばの意味をつめないで議論するから、同じことばでみアナ違うことをイメージしてしまう。それでもなんとなく判った気になってしまうからほとんどの議論が空中戦となり、徒労におわる。
ダメ教会を見分ける
そこにいったとしても、救われたと思えないなら、その教会に行かなくてもよい。
神学は「時代の哲学」を身にまとう
その時代における哲学的な表現を神学が利用することは経験的によく見られる。
歴史は発展する―シュライエルマッハーの近代主義
現在は過去の蓄積からなっている。それと同時に将来何をするかという未来からの圧力も加わっている。その中において永遠の今として、今のこの瞬間があるという考え方。
シュライエルマッハーは歴史進学主導の考え方をしている。歴史の発展とともにわれわれは進歩して、いつかは完成に向かうとしている。
すべては救済に関係づけられる
ところが、紅斑で通常の歴史神学に対して倫理学の学習が先行されるとする。
なぜか?それは救済という観点に即した決断をしてくことが倫理である。だから、倫理学的な関心が常に歴史神学に先行する。
神学研究の本質は、個々人の人間の救済、具体的な人間の救済であって、人類全体という抽象的なものではない。
「パンとブドウ酒」は何を意味するのか
実体変質説の様々な解釈
パンとぶどう酒は象徴であるが、そのもとでキリスト教が何を行ってきたかを知ることが重要である。
実体変質説ではパンはぶどう酒は、ミサを経て本当にキリストの体と血に変わってる、とする考え方から、単に象徴であると捉える考えなど、プロテスタント内でも意見が分かれる。
国家論としての「神学通論」
シュライエルマッハーの神学通論は、「教会」を「国家」に置き換えると国家論として読み直すことができる。彼の著作は過剰な解釈を可能にする。
2011年10月11日
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その1-
第3章キリスト教神学入門①知の全体像をつかむために
緒方純雄先生のアドバイス
神学のあらまし①-聖書神学と歴史神学
神学のあらまし②-体系知としての組織神学
神学のあらまし③-実践神学
大学で習得すべき語学とは?
「合理的」と「実証的」
すべては救済へ至る「道」
火宅の人、バルト
象徴ではなく思想が重要
教会は何のためにあるのか
緒方純雄先生のアドバイス
シュライエルマッハーの「神学通論」をポイントに即してみて行く。彼のナショナリズム観もこの本に一貫して流れている。この本は神学の書であるとともに国家についての学でもあった。
神学のあらまし①-聖書神学と歴史神学
神学のあらまし②-体系知としての組織神学
神学のあらまし③-実践神学
聖書神学、歴史神学、組織神学、実践神学の4つに分けられ、最も重要なのは実践神学である。なぜなら、キリスト教は救済宗教であり、実践神学を補助するために他の神学が存在する。
聖書神学:旧約聖書学と新約聖書学に分かれる。
歴史神学:教会史と教理史に分かれ、教会の歴史・教理の歴史について勉強する。
組織神学:教養学、倫理学、宗教哲学。16世紀に護教学として登場した。
実践神学:牧会学(牧師になった時どう信者と関係を作っていくのか、典礼の作法を学ぶ)、説教学(聖書の解釈)、教会音楽に分かれる。
大学で習得すべき語学とは?
旧制高校で必須だった、フランス語、ドイツ語、英語の3つ。
「合理的」と「実証的」
神学とは、その語がここで用いられている意味からすれば、一つの実証学的な学(eine positive Wissenschaft)である。
「実証的(ドイツ語のポジティフ、英語のポジティブ)」であるかどうかをどう判断するか?それは理性である。理性に基づく話は全員が共通して理解でき、皆の意見が一致する。
だから理性に基づく実証的な話は全員が賛成できる。
合理的であることも同じ意味だが、シュライエルマッハーはそれをあえてずらした。
つまり、合理と実証を切りはなした。そして、合理的であっても実証できないこともあるそして、逆もあるとする考え方が出てきた。
本質的には神は合理的な枠を逸した存在であり、合理性で完全に説明できるものはキリスト教の神としては異質なものだ、とした。
すべては救済へ至る「道」
学問とは体系的に対象を認知する、つまり「体系知」である。知識だけを蓄積しても意味がなく、方法論が必要である。
方法論とは「道」にようなもので、方法論が確定すると結論が決まる。
神学の最終目的は「神」である。そして、神を知ることが人間の救済になる。
神学の概略をしるには、カール・バルトの教会学義学がおすすめ。
火宅の人、バルト
愛人に口述筆記させて描いた。愛人が途中で亡くなったので中断した。
象徴ではなく思想が重要
第一節の注釈に、合理的神学は思弁的な学であって、われわれの神学とはまったく異なるとある。神学は理性的な学ではないとのことだが、これはヘーゲルへの当てこすりである。
「神学」は信仰の上に成り立っている。神学の無い信仰はあるが、逆はない。
第二節は以下の様な書き出しである。
ある一定の信仰の在り方が、それが象徴的行為よりも思想的表象によって自己を伝達するようになり、それと同時に歴史的な意義や自律性を獲得してくるに従い、その程度に応じて神学を形成するようになる。
ここでいう象徴的行為、とはひらたくいうとパンとブドウ酒を分け合う聖餐式や洗礼などの宗教的儀式である。
シュライエルマッハーはパンとブドウ酒などの象徴的行為ではなく、思想的な表現によって自己を示すのが神学だ、とする。また、思想的なもののレベルが上がるにつれて神学は発展していく。
この「哲学や思想の発展に合わせて神学も発展していく」という考え方が彼の受肉論解釈に当てはまる。彼の中には物事は常に発展していくという一種の進化論があり、人間の内面の絶対依存の感情は常に発展しており、絶えず自己表現を重ね、具体的な形に受肉していくとする。
教会は何のためにあるのか
神学はエリートの学問であり、それによって大衆を導いていく。シュライエルマッハーによるとすべての学問は神学の補助学である。神学とは体制側のエリートの学問である。だから、そのまま政治学に応用することも可能である。
教会は何のためにあるのか?キリスト教にとって、救済はイエスキリストが下りてきたことで始まっているが、まだ完了していない。終末(救済の完成)は遅延しているがその中で、救済は教会によって担保されている。
2011年10月07日
はじめての宗教論 左巻 -第2章 宗教とナショナリズム-
第2章 宗教はなぜナショナリズムと結びつくのか?
知的体系としての錬金術
魔術と啓示
カネ―とナショナリズムー二つの主流宗教
民族の揺籃となったカレル大学
教皇庁の堕落
道具主義の考え方
「想像の共同体」と尖閣諸島沖問題
ケドゥーリーの批判的考察
神は民族に受肉する?
同胞意識と排他性
死をも肯定するナショナリズムへ
知的体系としての錬金術
錬金術とは、何らかの作業を行って、いくつかの条件が重なることによって必ずひとつの結果が出てくる。これは魔術の手法であり、基本的には近代自然科学の手法と同一である。錬金術はと近代以前の一大知的体系であった。
魔術と啓示
現代の金融工学なども考え方の基本に錬金術がある。何らかの操作を加え、自分の資産の価値を増殖させている。
それに対し、宗教的な啓示はそれとは全く異なり、啓示には規則性がなく突然降りてきて、人間の実存自体を破壊してしまう力がある。それに対して、拒否するか従うかしかないというのがキリスト教の基本的な考え方である。
カネ―とナショナリズムー二つの主流宗教
シュライエルマッハーは宗教の本質を「直感と感情」と定義し、晩年には「絶対依存の感情」とした。
近代的人間は心は内側にあると考えた。内なる両親の声と神の声に差がなくなり、主観的心理と神の啓示も原理的には区別できなくなり、啓示と願望を混同する危険性が生じた。
キリスト教的な人間観では、人間は本質において超越的なものに憧れ、自己同一化していく存在である。たとえ、自分は無宗教者だと定義しても、無宗教という宗教に過ぎない。
また、最も主流の宗教というのは、宗教としてではなく慣習として意識されるのが常である。現代においては「拝金教」と近代におけるナショナリズムのふたつがある。
また、民族についても原初主義と道具主義の二つがある。
前者の原初主義は日本民族なら2600年続いている、中国なら5000年続いているといったような各民族が固有の言語や土地、経済に基づいているという考え方である。
しかし、実証的な歴史学においては全くナンセンスである、とされている。民族というのはきわめて近代的な現象でフランス革命以降に世界に広がり、長く見積もって250年くらいしかない。
民族の揺籃となったカレル大学
民族(nation)の原型はラテン語のナチオ(natio)である。これはかつて大学にいあった。中世期の大学はそもそも徒弟制のギルドであった。大体各大学に4つのナチオがあった。ナチオとは「国民団」などと訳されるが「郷土会」がより正しい。
民族の原型となったのはプラハのカレル大学のナチオであった。ここにはボヘミア、ザクセン、バイエルン、ポーランドのよつのナチオがあり、ボヘミアだけがチェコ語を話し、他はすべてドイツ語であった。
ナチオが政治的意味を持つようになったのは15世紀のフス派の反乱からである。それまでのナチオは出身地を一緒にするだけのサークルであった。大学の授業はラテン語で行われたが、サークルの中ではお国言葉が話されていた。同じ言語を話す人たちの間にひとつのコミュニケーション体系、文化ができてきて、それぞれのサークルで情報の集積量が変わってくる。そのため、民族が生まれるときの言語の役割が強い。
15世紀にフス派は清廉な生活と財産の公平分配をカトリックに対して、主張した。当時ボヘミアは派非常に豊かであり、その経済力と新しい軍事技術に支えられ、カトリックに全線全勝していった。
こうして、民族のアイデンティティとチェコ語という言語、フス派の宗教改革とが結びつき、民族と国家の一致を是とする国民国家、ネイション・ステートの考え方の基本が生まれた。
このフス派の反乱が原基形態が、似たような出来事が繰り返し起こり、徐々にドイツやフランスなどの民族が煮詰まり、その集大成が1789年のフランス革命であった。
教皇庁の堕落
このころ、カトリックの教皇庁の堕落はひどく、兵を雇って戦争をし、贖宥状をうって大もうけをしていた。これを見て、フスはローマ教皇は天国の鍵を持ってはいないと断じた。
道具主義の考え方
道具主義とは、エリート層が自分たちのポストを維持するために大衆を操作することで民族が創られる、という考え方。目的のために道具としてナショナリズムを利用していく。ナショナリズムが先行して国民国家が生まれてくる。
この考え方には、ベネディクト・アンダーソンの「想像の共同体 ―ナショナリズムの起源と流行―」に詳しい。
出版資本主義では世俗語で書かれた書物で金儲けをする。その結果、世俗語で書かれたその書物を読む読書人たちを中心とする、情報を共有するひとつのグループが出来上がる。それによって、世俗語を単位としてある人々と別の人々という区分ができ、このような区分がナショナリズムの起源と考えた。
このようなアンダーソンの考え方では民族とは想像された政治的共同体、すなわち想像上の存在となる。
このようにして出来上がった国家の特徴を、アンダーソンは「主権的であること」と捉える。すなわち、国家が国民に一方的に強制できる。つまり、徴兵と徴税ができる。
もうひとり、道具主義の主要な論客にアーネスト・ゲルナーがいる。彼は産業資本主義と民族と国家というのは一種の三位一体的な関係にある。
「想像の共同体」と尖閣諸島沖問題
このような道具主義的な考え方から見ると、さきごろおこった尖閣諸島沖問題もみえてくる。この問題の背後には中国が現在、本格的に近代化が進み、それに伴い国民国家的なものの建設(ネイション・ビルディング)が行われていることがある。
ネイション・ビルディングには「敵のイメージ」が不可欠である。敵に対抗することで「われわれ」が一丸となる。中国にとって、日本は敵のイメージを担っている。
これは中国の近代が終焉を迎えるまで続くだろう。
ケドゥーリーの批判的考察
エリー・ケドゥーリーはナショナリストとしてのシュライエルマッハーの側面を非難した。
シュライエルマッハーは神の場を人間の内部に定義することによって、内部と外部を混同し、啓示と願望を混同する危険性が生じた。
われわれは心の中に神の声が聞こえるから、断固自分の信じる道を行け、ということになる。
それが、<政治的行動への真の指針とみなされるようになった>結果、第一次世界大戦という大量殺戮がもたらされたとした。
神は民族に受肉する?
では、シュライエルマッハーとナショナリズムはどうのように結びつくのか??
その考え方の基礎に「受肉論」がある。「受肉論」とは神と人間をつなぐ媒介項として、「真の神で真の人」であるイエス・キリストが出現した。天上の神がイエス・キリストという人間になること、それが受肉である。
シュライエルマッハーの考え方を受肉論に基づいてみてみる。
心の中にある絶対依存の感情が、歴史において受肉して、具体的な形をとる。それこそが民族(ネイション)であり、国家(ステート)であり、両者が一体となった国民国家(ネイション・ステート)という形態である。このようにして、ひとつの言語、ひとつの民族、ひとつの国家という近代のネイションステート的発想が固まっていく。
なぜ、こうなってしまったかというと、受肉論に輪廻転生の考え方が混じったからだと考えられる。シュライエルマッハーはプラトンの翻訳も行った。その過程で、神秘主義的なネオプラトニズムが混じった可能性がある。
シュライエルマッハーの一番の問題点は、イエス・キリストという固有名詞が希薄になってしまったことである。
同胞意識と排他性
国家が外国人の王朝によって征服されることに対する強い反発によって同法意識が生じてくる。ここでベネディクト・アンダーソンが言うところの公定ナショナリズムが生まれる。それを操作して、支配者層が自分たちは民族=国民の代表者であるという表彰をうまく作り上げ、下で生じた同朋意識をうまくまとめる。その結果、敵のイメージを担う「外国人」たちは排除されることとなる。
死をも肯定するナショナリズムへ
ナショナリズムは不完全な世界から離れ、内部に目を向ける。現実世界に対するこのような軽蔑は究極的には生への拒絶と死への愛となる。
<外部から何の支えも必要としない心の底からの確信>によって、人間の自己絶対化を規制する枠がなくなってしまい、上記のナショナリズムの歯止めが利かなくなってしまい大量殺戮の戦争へと至った。
神の場が内部に転換することで、神の声と内なる良心とに区別がつかなくなり、自らの願望と啓示が混同されてしまった。そこに、ネイションへの信仰が結びつくと、あからさまなナショナリズムや死への信仰が生じることとなった。
タグ :佐藤 優
2011年10月06日
はじめての宗教論 左巻-第1章 近代とキリスト教-
第1章 近代とともにキリスト教はどう変わったのか?
<目次>
ソ連の無神論教育
ドイツにおける全集の作り方
形而上と形而下
「直観と感情」のインパクト
宗教と道徳はおなじものか
カトリックの教義とプロテスタントの教義
教義・教理・思想
道徳の危険性
プロメテウスは何を象徴するのか
エンサイクロペディアの含意
趣味としての宗教?
外部と内部の混同
ソ連の無神論教育
ソ連では農民を飛行機に乗せて、雲の上を見せ「空の上に神がいない」と言う事を証明しようとした。一部では影響力を持ったが長くは続かなかった。
ドイツにおける全集の作り方
シュライエルマッハーの全集が出始めているが我々の生きているうちには完成しないと思われる。重要な人物は200年くらいかけ、特別に編集スタッフを一から養成しノウハウを引き継いで作っていく。
形而上と形而下
[宗教の根本定義。それは宇宙の直感と感情。かくして、それは形而上学と道徳と相並ぶところの人間精神の本質的必然的第三者。]/これを以て、宗教はその財産を占有せんがためには、形而上学や道徳に属するものにたいするあらゆる要求を断念し、宗教に押しつけてあるものはすべてこれに返却する。宗教は、形而上学のように宇宙をその性質に従って規定しかつ説明しようとは欲しないし、道徳のように自由の力、および人間の心的自由意思から宇宙を発展させ、かつ完成させようとは欲しない。宗教の本質は、思惟でも行為でもなく、直感と感情である。(シュライエルマッヘル「宗教論」佐野勝也、石井次郎訳 岩波文庫、1949年)
最後の「直観」と「感情」がキーワード。
シュライエルマッハーは別の著書で、宗教は<形而上学と道徳とに対立する>としている。
まず、「形而学上」とはなにか。「有形の器すなわち自然の形象を超えた無形の道すなわち原理の学の意」である。これはもともとアリストテレスの考え方に由来し、それが神学に入り込んで形而上学となった。そして、アリストテレスの体系を使いながらキリスト教について説明するようになった。
反対は「形而下」だがこれは我々の住んでいる世界の現象の事をさし、通例「自然学」とよばれる。
「直観と感情」のインパクト
それでは、形而上学的に考えると神はどこにいることになるのか?
雲も月も突き抜けたずっと「上」である。
しかし、コペルニクス革命によって天動説が地動説にパラダイムシフトし、形而上学的な神様では都合が悪くなった。
つまり、上にあるとされた神の居場所が天動説から地動説に代わることで物理的に証明できなくなった。そのときにシュライエルマッハーは感情と直観という形で神の居場所を人間の心の中に定義しなおした。
形而上学的な世界観のもとで、神と宇宙像が完全に二元化してしまった(神の居場所と宇宙が完全に分離した)。
宗教と道徳はおなじものか
宗教は道徳に対立する、とされた。
道徳は「一般的に正しいとされる考え」で、倫理は「自分がこうあるべきだという考え」のことである。
なおシュライエルマッハーはこの時、カントを念頭に置いている。カントにとっては神と道徳は同じものである。道徳的に正しいことをしていれば、それは神の道に適うという事になってしまい、宗教と道徳が同じになってしまい、それは神学的にはよろしくない。
なぜ一緒にしてはいけないのか、というと、人間と神を同一視することになってしまうからである。これは自己神格化といい、キリスト教では絶対に認められない事である。
このように自己神格化につながるため、シュライエルマッハーは宗教と道徳の混同を拒否した。
カトリックの教義とプロテスタントの教義
カトリックには神の啓示を形にした教義(ドクトリン。数学でいう公理系)があり、それに基づいているからローマ教皇は信仰と道徳について不可謬性がある、とされる。
一方、プロテスタントの教義は結論から言うとそれはわからない。イエスキリストが救い主である、と言う事ぐらいである。
教義・教理・思想
教義:ゆるぎない真理
教理:それぞれの教会が正しいと思っていること
キリスト教思想:神学者たちが教会の立場とは別にもつ自分の考え
となる。
道徳の危険性
プロメテウスは何を象徴するのか
エンサイクロペディアの含意
趣味としての宗教?
シュライエルマッハーによると、宗教の本質は、思惟(形而上学)でもない、行為(道徳)でもない。ではなにかというと、それは直観と感情であるという。
そして、その直観と感情は外側からもたらされる、とした。
一方、道徳は自由意識から出発し、人間が正しいと思うことによって自然界を克服し、外へと拡張していくという考え方である。
シュライエルマッハーは「宗教なくして思索と実践とを所有しようとするのは大胆なる傲慢である」、とし、それらをプロメテウス的な不遜であると戒めた。
彼は宗教、形而上学(思索)、道徳(実践)の三者併存の世界を考えていた。
そして、宗教は「趣味」つまり、他人に押し付けることができない、とした。
外部と内部の混同
シュライエルマッハーの「宗教論」では宗教の定義は「直観と感情」であったが、晩年にあるとこれが「絶対依存への感情」へと変化する。
前者ではまだしも外部性が保たれていたが、後者では「絶対」と「依存」、そして「感情」が結び付くことで、神の場は完全に人間の自己意識の中に封じ込められてしまう。
つまり、外部と内部が混同され、人間は宇宙を直感でとらえる力を主体的にもっているという形になってきた。そうすると人間の主観と宇宙を総べる意志の違いはなくなってしまい、我々は神というリアルな感覚を持てなくなってしまった。
タグ :佐藤 優