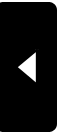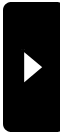2011年10月05日
はじめての宗教論 左巻 -序章-
難しくてわかんないところは読み飛ばしているけどっ。
気にしないっ。
気を取り直してレッツ・ゴー左巻ヽ(゚∀゚)ノ!
=========================
<目次>
序章 キリスト教神学は役に立つ―危機の時代を見通す知
第1章 近代とともにキリスト教はどう変わったのか?
第2章 宗教はなぜナショナリズムと結びつくのか?
第3章 キリスト教神学入門①知の全体像をつかむために
第4章 キリスト教神学入門②近代の内在的論理を読み解く
第5章 宗教は「戦争の世紀」にどう対峙したのか?
第6章 神は悪に責任があるのか?危機時代の倫理
================================
序章 キリスト教神学は役に立つ―危機の時代を見通す知
<目次>
古プロテスタンティズムと近代プロテスタンティズム
「自由主義神学」登場の背景
シュライエルマッハーの功績と限界
宗教による宗教批判
左巻のあらまし
序章 キリスト教神学は役に立つ―危機の時代を見通す知
左巻の主題は「宗教はなぜナショナリズムと結びつくか」「人間は近代、ひいては宗教を超克できるのか」。
キーパーソンは「近代プロテスタント神学の父、自由主義神学の父」フリードリッヒ・シュライエルマッハーである。
古プロテスタンティズムと近代プロテスタンティズム
プロテスタンティズムは二期に分かれ、それぞれ古プロテスタンティズムと近代プロテスタンティズムとよばれる。
前者は16-18世紀で啓蒙主義が起こるまでの時代であった。後述するようにプロテスタンティズムは、近代のより前の世界像に合致するような世界観の原始キリスト教へ戻れという復古主義運動だった。
18世紀以降を近代プロテスタンティズムとよぶがその差はひとことでいうと、後述するが「神の場」が転換していることにある。つまり、天上にあった神の場が人々の内面に降りてきた。言い換えるなら近代以前の世界観から啓蒙主義への転換である。
18世紀に流行した啓蒙主義が政治に反映して、歴史の画期となったのがフランス革命であり、啓蒙主義の限界が露呈したのは第一次世界大戦であった。これを「長い19世紀」と呼ぶ学者もいる。
そんな長い19世紀の始まりの時点で、シュライエルマッハーやカントや、ヘーゲルやシェリングは啓蒙主義の限界を感じ、それぞれのやり方で克服した、もしくは克服を試みた。
「自由主義神学」登場の背景
テキストクリティークを一例に取ると、プロテスタントは登場当初、逐語霊感説や十全霊感説が主流であり、無茶苦茶な聖書理解を行っていた。
このような古プロテスタンティズムの行き過ぎをひっくり返す必要が生じ、近代プロテスタンティズムとともに自由主義神学が出てくる。
プロテスタンティズムはそもそもが復古維新運動から発生し、反知性的であったが18世紀に登場した啓蒙主義を乗り切って、啓蒙主義と併存することに成功した。その決定的な役割を果たしたのがシュライエルマッハーであった。
シュライエルマッハーの功績と限界
では、シュライエルマッハーはどのようにプロテスタンティズムと啓蒙主義を併存させたのか。
そもそも人間にとってキリスト教の神は「見えない世界」にいる。近代以前は神が天上に存在することに誰も疑念を持たなかった。
しかし、コペルニクス以降、地動説が主流になり、マゼランにより地球が球体であることが証明されると、「天上の神」を思い浮かべることが出来なくなってしまった。
この問題を「宗教の本質は直観と感情である」「宗教の本質は絶対依存の感情である」と定義し、シュライエルマッハーは神は天上ではなく、各人の心の中にいることにした。神を「見えない世界」にうまく隠し、神の居場所問題を解決した。
しかし、ここから、人間の心理作用と神を混同してしまう新たな問題が派生した。そしてまた、絶対者を心のなかに置くと、その位置にネイション(民族)が忍び込んでくる。ここに国家・民族という大義が生命より大事であるという観念が生まれ、その延長に第一次世界大戦が勃発し、啓蒙主義の限界が露呈した。
ここに第一次世界に面して、自由主義神学も崩壊した。各国の自由主義神学者はおおむねが自国の戦争政策を支持し、大量破壊と殺戮を前に、神学は無力さを露呈した。
宗教による宗教批判
その結果、カール・バルトたちのいわゆる弁証法神学(危機の神学)が生まれた。
バルトは宗教そのものも人間自らの願望を投影した偶像崇拝であるという認識が登場し、神の圧倒的な啓示の力によって宗教批判を徹底していくのが神学の課題とされた。
一方バルトとならぶ弁証法神学者のフリードリッヒ・ゴールガルデンは神の超越性よりも、人間の「決断」を重視するようになった。
彼は危機の時代にはドイツ民族としての大胆な決断が必要と考え、カリスマを持つアドルフ・ヒトラーに賭けることとなった。
左巻のあらまし
(略)
気にしないっ。
気を取り直してレッツ・ゴー左巻ヽ(゚∀゚)ノ!
=========================
<目次>
序章 キリスト教神学は役に立つ―危機の時代を見通す知
第1章 近代とともにキリスト教はどう変わったのか?
第2章 宗教はなぜナショナリズムと結びつくのか?
第3章 キリスト教神学入門①知の全体像をつかむために
第4章 キリスト教神学入門②近代の内在的論理を読み解く
第5章 宗教は「戦争の世紀」にどう対峙したのか?
第6章 神は悪に責任があるのか?危機時代の倫理
================================
序章 キリスト教神学は役に立つ―危機の時代を見通す知
<目次>
古プロテスタンティズムと近代プロテスタンティズム
「自由主義神学」登場の背景
シュライエルマッハーの功績と限界
宗教による宗教批判
左巻のあらまし
序章 キリスト教神学は役に立つ―危機の時代を見通す知
左巻の主題は「宗教はなぜナショナリズムと結びつくか」「人間は近代、ひいては宗教を超克できるのか」。
キーパーソンは「近代プロテスタント神学の父、自由主義神学の父」フリードリッヒ・シュライエルマッハーである。
古プロテスタンティズムと近代プロテスタンティズム
プロテスタンティズムは二期に分かれ、それぞれ古プロテスタンティズムと近代プロテスタンティズムとよばれる。
前者は16-18世紀で啓蒙主義が起こるまでの時代であった。後述するようにプロテスタンティズムは、近代のより前の世界像に合致するような世界観の原始キリスト教へ戻れという復古主義運動だった。
18世紀以降を近代プロテスタンティズムとよぶがその差はひとことでいうと、後述するが「神の場」が転換していることにある。つまり、天上にあった神の場が人々の内面に降りてきた。言い換えるなら近代以前の世界観から啓蒙主義への転換である。
18世紀に流行した啓蒙主義が政治に反映して、歴史の画期となったのがフランス革命であり、啓蒙主義の限界が露呈したのは第一次世界大戦であった。これを「長い19世紀」と呼ぶ学者もいる。
そんな長い19世紀の始まりの時点で、シュライエルマッハーやカントや、ヘーゲルやシェリングは啓蒙主義の限界を感じ、それぞれのやり方で克服した、もしくは克服を試みた。
「自由主義神学」登場の背景
テキストクリティークを一例に取ると、プロテスタントは登場当初、逐語霊感説や十全霊感説が主流であり、無茶苦茶な聖書理解を行っていた。
このような古プロテスタンティズムの行き過ぎをひっくり返す必要が生じ、近代プロテスタンティズムとともに自由主義神学が出てくる。
プロテスタンティズムはそもそもが復古維新運動から発生し、反知性的であったが18世紀に登場した啓蒙主義を乗り切って、啓蒙主義と併存することに成功した。その決定的な役割を果たしたのがシュライエルマッハーであった。
シュライエルマッハーの功績と限界
では、シュライエルマッハーはどのようにプロテスタンティズムと啓蒙主義を併存させたのか。
そもそも人間にとってキリスト教の神は「見えない世界」にいる。近代以前は神が天上に存在することに誰も疑念を持たなかった。
しかし、コペルニクス以降、地動説が主流になり、マゼランにより地球が球体であることが証明されると、「天上の神」を思い浮かべることが出来なくなってしまった。
この問題を「宗教の本質は直観と感情である」「宗教の本質は絶対依存の感情である」と定義し、シュライエルマッハーは神は天上ではなく、各人の心の中にいることにした。神を「見えない世界」にうまく隠し、神の居場所問題を解決した。
しかし、ここから、人間の心理作用と神を混同してしまう新たな問題が派生した。そしてまた、絶対者を心のなかに置くと、その位置にネイション(民族)が忍び込んでくる。ここに国家・民族という大義が生命より大事であるという観念が生まれ、その延長に第一次世界大戦が勃発し、啓蒙主義の限界が露呈した。
ここに第一次世界に面して、自由主義神学も崩壊した。各国の自由主義神学者はおおむねが自国の戦争政策を支持し、大量破壊と殺戮を前に、神学は無力さを露呈した。
宗教による宗教批判
その結果、カール・バルトたちのいわゆる弁証法神学(危機の神学)が生まれた。
バルトは宗教そのものも人間自らの願望を投影した偶像崇拝であるという認識が登場し、神の圧倒的な啓示の力によって宗教批判を徹底していくのが神学の課題とされた。
一方バルトとならぶ弁証法神学者のフリードリッヒ・ゴールガルデンは神の超越性よりも、人間の「決断」を重視するようになった。
彼は危機の時代にはドイツ民族としての大胆な決断が必要と考え、カリスマを持つアドルフ・ヒトラーに賭けることとなった。
左巻のあらまし
(略)
2011年10月02日
はじめての宗教論 右巻 ー第6章 宗教と類型ー
第6章 宗教と類型-日本人にとって神学とは何か?
<目次>
キリスト教における類型とは?
モナドロジーの考え方
「全体」には複数ある
クロノスとカイロス
歴史と類型
キリスト教をどう土着化させるか
創造神話という地盤
日本キリスト教の実践的課題
アジア類型のキリスト教?
魚木神学の功績
優れた神学書の条件
具体化されなけば無意味である
倫理という過酷な決断
再び、なぜ宗教を考察するのか
神の場の転換
キリスト教における類型とは?
宗教は文化の一形態。
純粋なキリスト教はありえず、文化と融合して成立する不純なもの(類型)。
キリスト教には文化の数だけ類型がある。
モナドロジーの考え方
「全体」には複数ある
ドイツは哲学が発展したが、それにはライプニッツが大きな貢献をした。
ライプニッツはカトリックとプロテスタントを統合しようとした。彼の考えはモナドロジー(単子論)とよばれている。
モナド(単子)はお互いに完結していて、出入りする窓を持っていない。神によらずして生じることもなければ、神によらずして消えることもない。
極小のものから極大のものまでモナドが無数にあり、神によってつくられたモナドにはそれぞれ風船のように紐がついていて、その紐は神のところでおさえられているのでモナド間の交通は神を経由することによって可能となる。
クロノスとカイロス
クロノス:順番に流れていく時間
カイロス:タイミング
クロノスに対してカイロスが介入してくる、つまり順番に流れる時間に特定の出来事が介入することで物事が変化する。
クロノスに基づいて歴史をまとめると、ドイツ語のヒストリー(編年史)。
カイロスとクロノスを結び付けて物語を作ると、ドイツ語のゲシヒテ(歴史、英語のヒストリー)となる。
歴史と類型
きわめて近代的。どの出来事がどういう意味があるか、というのは現在の時点からの特定の視点が必要で歴史観が重要となる。
それぞれの国から見たそれぞれの世界史がある。
唯一絶対の世界史は存在せず、そこから、類型という考え方が出てくる。
キリスト教をどう土着化させるか
キリスト教の本質を理解するには、歴史についての反省と検討が必要。キリスト教には聖書があるが、それだけではわからず、現代神学だけでもわからない。キリスト教は日本とは異なる歴史的経緯によって出来上がったのもであるので、歴史についての理解が必要。
日本でももちろん、キリスト教は日本的な類型としてあらわれてくる。
日本でが救われるために知識を身に着ける仏教が先にあったため、キリスト教の本質が救済宗教だと早く気づけた。
しかし、仏教が救済に関して見事なドクトリンを展開しているため、相当掘り下げないとキリスト教に帰依するものがいなくなる。
創造神話という地盤
日本の神々が無から物事を作り出す創世神話は、キリスト教の創造信仰と類似しており、受け入れられやすかった。
日本キリスト教の実践的課題
アジア類型のキリスト教?
魚木神学の功績
本書で作者が意図するのは、類型を突き抜け普遍的なものに至ることである。
日本の優れた神学者、魚木は特権を持ったことのないキリスト教教徒は、日本の宗教的土壌・伝統に根付いている救済という概念を通して、キリスト教という流れに行きついたのであるという一種の土着論化を行った。
優れた神学書の条件
読むと同時に自分も読まれる。融合と対話が起こってくる。
具体化されなけば無意味である
倫理という過酷な決断
現代日本にもさまざまな苦難に満ちている。苦難の根元には悪がある。そして、悪を生み出したのが人間の罪である。イエスはこのような苦しむ人たちと正面から向き合い、行動することによって悪と戦った。
受肉について。
全知全能の絶対的な神は字お重速吸うrことを望まず、また罪を犯した人間を滅亡させることもせずに、神の一人子をこの世に送り、仲介者とすることで、人間を救うという決断をした。ここから受肉論を基礎に倫理を考える。
理念とは必ず具体的な何かに受肉する。必ず形をとる。受肉論がキリスト教の大きな特徴である。
社会においても生じる。たとえば貨幣である。
人間の行動も受肉によってすべては個別的な出来事になっている。
再び、なぜ宗教を考察するのか
神の場の転換
神無き世俗化の時代、ヒューマニズムの時代において人間の合理性の実が突出し、自分たちが思う形で世の中を設計できると思ってしまう。それによって神の座に自分を置いてしまう。そのために色々なトラブルが起きている。これが偶像崇拝の罪である。
神の啓示は我々の外から訪れ、人間のちっぽけな実存を破壊する。
しかし、近代になるとこのような外部性は捨象され、人間の内面が肥大化していく。人間の自己絶対化はここから生じた。
近代は自己完結した「内面の世界」が誕生するとともに、厄災の時代が始まった。
タグ :佐藤 優
2011年10月01日
はじめての宗教論 右巻 ー第5章 人間と原罪ー
第5章 人間と原罪-現代人に要請される倫理とは?
<目次>
ただ、イエス・キリストを通じてのみ
ドイツ語アレルギー克服法
不当拡張と責任回避
現在はどこから生じるのか
なぜヨーロッパには化け猫はいないのか
仏教とキリスト教の生命観の違い
聖書学の二つの流れ
カール・バルトの啓示至上主義
類比的思考の意義
「身代金」とはどういう意味か
「関係の類比」と部落解放の神学
「存在の類比」とエコロジー神学
受肉とは何か
イエスは神か人間か-2つの論争
ロシア革命の精神的背景
宗教改革の本質
「世界教会」という考え方
イエズス会と典礼問題
信者にぶどう酒を飲ませない理由
ユニア教会、登場
<要約>
ただ、イエス・キリストを通じてのみ
ドイツ語アレルギー克服法
神について直接知る手段はイエス・キリストによってのみである。なぜならイエスは真の人であるとともに真の神であるからだ。
特にプロテスタントはイエスは聖書を通じて知ることができる、としている。
聖書研究にはドイツ語が必修である。
不当拡張と責任回避
原罪はどこから生じるのか
エデンの園で智慧の実を食べたアダムとエバは神に詰問された。その中で神の言った事を不当に拡張し、責任を他人に被せる行為が見られた。それが神を怒らせた。このやりとりに原罪が見られる。
なぜヨーロッパには化け猫はいないのか
仏教とキリスト教の生命観の違い
仏教では人間と動物の区別がない。なぜなら、両方痛みを感じるからである。一方、キリスト教では人間は神から「プネウマ」を吹き入れられた。しかし、他の動物はそうされていない。だから人間は特権的な地位にある。その特権的な地位とは、神の似姿であるがゆえに自由意思を持っていることである。
この自由意思を使って人間は必ず悪い選択をする。これがプロテスタンティズムの考え方である。
一方、カトリシズムは神の恩寵によって人間は正しい選択もできる、と考える。
聖書学の二つの流れ
19世紀、イエスが実在していることを証明することは難しかった。これを踏まえ、聖書学は二つの流れになった。
ひとつは無神論。聖書は神という名前に仮託して理想的人間について述べられているにすぎないという発想で、フォイエルバッハが集大成した。
もう一つはイエスに関する物語を解釈していく立場である。1世紀のパレスチナにおいてイエスという人間がいたと証明はできないが、2世紀にはイエスを信じる人々がいたと言う事は実証できる。そこから探求を開始する態度である。
カール・バルトの啓示至上主義
カール・バルトは人間が表彰する神は、人間の願望が投影されたにすぎないと考える。人間は神とは全く異なるが、人間は神について語らないといけない。なぜなら、人間は神に連なることによってのみ救済されるからである。
神はイエスを地上に使わされた。そのことによって救済は先取りされている。
このような指針のもとでは、「宗教(人間が作り出した幻影)」とキリスト教はぶつかる。
キリスト教が伝えているのは「啓示」である。啓示によって宗教という幻影を破壊していくのがキリスト教のメッセージである、とする。
類比的思考の意義
「身代金」とはどういう意味か
「関係の類比」と部落解放の神学
「存在の類比」とエコロジー神学
神が人間を創造したの如く創造者と被創造者の関係性を、たとえば、神の中にある秩序に従っている、として、王侯貴族の農民支配に適応するのは「関係の類比」を単純化しすぎである。
類比は常識的思考で考える場合、必ず「破れ」がある。
受肉とは何か
イエスは神か人間か-2つの論争
神と人間の媒介項としてイエスキリストがいる。
キリスト教には神と人間を繋ぐ媒介項がある。これが、他の宗教と際立った違いである。
神が人になる、というのがキリスト教神学における受肉である。
マリアは原罪を持っているか否かが問題となった。正教とプロテスタントは持っているとし、カトリックは持っていないとした(テオトコス論争)。
キリストが人か神かとの議論もあった(ホモウシオス論争)。この場合、キリストの本質は神と一致するとした。
ロシア革命の精神的背景
プロテスタントとカトリックは、神から人間に至る啓示は砂時計の括れた部分を通じてやってくる、上から下の方向しかない。
しかし、正教は双方向を強調する。
正教ではヨウ狂者者という聖人がいる。
要は精神病者でロシアの聖人の1/3は彼らである。尋常でない行動をする彼らを神に連なると考え、精神の変調を神の啓示や聖霊の働きと見た。
人が神になるのが可能ならば、天国を現世に作ることも可能であると考え、このような刷り込みがロシア人にあったため、ロシア革命のような無謀な実験が起きた。
宗教改革の本質
「世界教会」という考え方
宗教改革はルネッサンスの後に起きた。
ルネッサンスはギリシャやローマの古典に還れという運動である。ルネッサンスは復古運動であり、理性への信奉があり、啓蒙主義とつながる側面を持つ。
しかし、16世紀の宗教改革には啓蒙主義につながる要素はない。中世期にスコラ哲学によって緻密な哲学・神学体系ができたがそれでは救われた実感は起きず、教会は世俗の権力と癒着し腐敗している。だから、宗教改革でイエスの唱えた素朴な原始教会に戻ろうとする。しかし、これは反知性的な運動であった。彼らは聖書を世俗語に翻訳した。
「宗教改革」とはプロテスタント側の解釈でカトリック側では「信仰分裂」としている。もういちどキリスト教として再統合しようという運動(エキュメニズム:教会一致促進運動)がある。
イエズス会と典礼問題
復古主義的なプロテスタント運動に対し、カトリックはそれ以上の改革を行い、イエズス会という教派を作った。これはローマ教皇庁に直結していた。その中心は、イグナチウス・デ・ロヨラやフランシスコ・ザビエルである。
ロヨラは軍人で、上意下達の官僚的なヒエラルキーで組織を作った。近代官僚制の基本もイエズス会から生まれている。また、インテリジェンス(特殊情報活動)の方法を用いる。キリスト教の本質に触れる部分は絶対に譲ってはいけないが他は妥協しても構わない、とする。
信者にぶどう酒を飲ませない理由
カトリックでは聖餐式は実態変質説にたつ。パンはほんとうにキリストの体となり、ブドウ酒はほんとうにキリストの血となる。それをこぼすと神聖冒涜になる。だから信者は辞退する、とする。
一方のプロテスタントは信者と神父に壁があるのはおかしいので、信者にワインを飲ませようという運動を始めた。
ユニア教会、登場
カトリックの対抗軍はすごいパワーで正教会の領域であるウクライナまで進行し、危うく大戦争となるところだった。
それはイエズス会としても勢力がそがれて困るので、ユニア教会、という教会を作った。そして「ロシア正教の慣習は何も変えなくていいから、ローマ教皇が一番偉い、聖霊が父及び子から出るこの2点だけを変えてください」とモスクワ主教に嘆願したところ、モスクワ主教もそれぐらいなら本質は変わらないから大丈夫だろうと了解した。しかし、そのうち異なったアイデンティティをもつ連中が出現した。
メンタリティがカトリックになったからである。
タグ :佐藤 優
2011年09月30日
はじめての宗教論 右巻 ー第4章 キリスト教と国家ー
第4章 キリスト教と国家-啓示とは何か?
<目次>
ポルターガイスト騒ぎ
ユダヤ教への改宗
キリスト教の創設者は誰か?
教会本来の運営原則
石打刑のしきたり
啓示の本質
使徒たちの内ゲバ
聖書の行間を読む
なぜ「イエス・キリストの名」なのか
固有名詞という問題
パウロの人間力
ギリシャ哲学の3つの派
貨幣もまた偶像である
「肉体」をめぐるすれ違い
税金は絶対に払え!
終末の到来
黙示録の革命的要素
悪の数字666
<要約>
ポルターガイスト騒ぎ
キリスト教の成り立ちを聖書に即してみていく。
使徒言行録に
「五旬祭がきて、使途が一堂に会していると、突然、激しい風が吹いて、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、ひとりひとりの上にとどまり、‘霊‘に満たされ、他の国々の言葉で話し出した」
とある。この「突然激しい風が吹いて」との記載がある。
これはプネウマのことである。霊が来て、ポルターガイストのようにガタガタと家を揺らす。
また「炎のような舌が分かれ分かれに現れ、ひとりひとりの上にとどまった」とある。
これは言葉のことである。
つまり、みな、酒を飲んで相当出来上がっているところに、聖霊が現れて、扉をがんがんたたいて、炎のようにワーッと喋り始めた。これが教会誕生のときで、外部からは酔っ払いの集団のように見えた。
キリスト教の創設者は誰か?
教祖はイエス、開祖はパウロである。
教会本来の運営原則
本来は持っているものをみなでわかつ。150人くらいの顔が見える範囲での共産主義的な生活であった。
外の世界でいやな目にあっても、この教会の中ではみながイエスの教えに従うし、金がなくても食っていける、地上における神の国とした。
石打刑のしきたり
啓示の本質
使徒たちの内ゲバ
聖書の行間を読む
最初の殉教者ステファノが出る。彼は石打ちという残酷な刑罰でなくなった。
そのステファノの殺害に賛同したサウロという悪いヤツがいた。
彼はキリスト教の迫害にたいそう熱心であったが、突如天から光が降りてきて、サウロは地に倒れる。
その後、キリスト教のアナニアがたずねてきて、あの光はイエスからの啓示だったとつげた。サウロはパウロに改名し、キリスト教の開祖となった。その後、ギリシャ語を喋るユダヤ人、非ユダヤ人にキリスト教は広がったが、エルサレムにいるペテロたちとぶつかるようになった。
ペテロたちの主張は「革命のためにはまずプロレタリア的な等をきちんと作って、思想的・組織的・運動的にユダヤ教の連中ののりこえを実現する。そのような形で革命に備えるべきだ。」
パウロたちの主張は「この世の終わりはもう近い。だから一刻も早くないランを革命に添加せよ、そのためには今までの経緯にこだわらずどんな連中であれ仲間に入れて強化したほうがよい」。
最終的な救済という目的は同じだが、戦略に差が出る。
現在はペテロの系統は途絶え、パウロの系統が残るのみである。
なぜ「イエス・キリストの名」なのか
固有名詞という問題
プロテスタントは最後に「主イエス・キリストの御名において」ととなえ、カトリックは「父と子と聖霊の御名において」ととなえる。どちらにせよ誰かの名前を通して、神との取次ぎを頼まないといけない。
律法を遵守してトーラーを読み、そのとおりに行動している天でイエスの信者たちはパリサイと変わらない。しかし、イエスの名によって神に救ってもらおうとしているところが決定的な違いである。
パウロの人間力
ギリシャ哲学の3つの派
貨幣もまた偶像である
「肉体」をめぐるすれ違い
税金は絶対に払え!
パウロは頭もよく、ユーモアがあり非常に人をひきつける要素があった。
しかし、パウロの説くキリスト教は当時のヘレニズムの知的世界ではナンセンスであった。
当時のギリシャにはエピクロス派(知的な快楽を求める)、ストア派(禁欲)、キニク派(シニカルで何も求めない)があった。しかし「肉体は魂にとっての牢獄だ」という考え方が当時のローマでは一般的で、いずれの派もパウロの説く「死者の復活」は受け入れがたかった。そのため、パウロが外国の新しい神を宣伝しにきたと考えていた。
一方のパウロも当時のアテネでみなが偶像を拝んでいるのを見て驚いている。
当時のアテネは文化の爛熟期を過ぎて衰退が始まっていた。退屈していた人々のもとにパウロは飛び込んでいって、大演説を始める。
パウロはが身が一人の人間からあらゆる民族を作り、地上のいたるところに住まわせ、季節を決め、居住地の境界を決めた、と述べた。
大切なのは境界で、みなそれぞれ自分の領域でがんばりなさいといった。
パウロは税金は必ず払え、為政者は尊敬しろと畳み掛ける。
その上で、偶像崇拝を戒めた。
パウロの伝道はおおむね成功したがアテネでは失敗した。なぜなら先ほど述べたように肉体をめぐるすれ違いがあったからである。
終末の到来
黙示録の革命的要素
悪の数字666
同じ聖書でも国家に批判的な場合はヨハネの黙示録を参照し、親体制的な場合はローマの信徒への手紙を参照する。
その、ヨハネの黙示録では延々と終末期の様子がつづられる。
イエスの弟子たちは近未来にこの世の終わりが来ると考え、イエスの言説について書き残すよりも早く改心して、この世の終わりに備えよ、というイエスの教えを広めることに尽力した。
しかし、週末はいまでたってもきていない(終末遅延の問題)。
こうして地上はだんだん混乱してくる。するとその混乱を収めるために強い国家、強い権力者が現れるが、ここでは『獣』と表彰され、国家への忌避が感じられる。
ヨハネの黙示録13章には「二匹の獣」の記述がある。
「獣」の背後にはサタン、竜が着いている。国家の背景には悪魔がいる。この「獣」には<大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられた>とある。だから国家は「美しい国」とか「毅然たる政策を遂行する」と大言を吐く。そしてこのような国家を拝む人間は偶像崇拝に当たるため、絶対に救われないと明言されている。
黙示録は地上の権力を認めない、革命的な姿勢が強く打ち出され為政者から忌避されることが多い。
では、国家にはどのように抵抗すればよいのか?
それは圧倒的な権力に対して革命を起こして理想的な社会を作ることではなく信仰を維持すること。そうすれば向こう側から、神のほうから救済が来る(千年王国)とされている。しかし、その後に第二の国家がやってくる。(666はキリスト教徒を迫害した暴君ネロの数字)。 黙示録でもっとも大事なのは竜で表彰される国家の外部性である。
キリスト行為とって聖書とは人間の知恵によって作られたものではなく、外部からの強烈な啓示が人間に降ってきた結果出来上がったもの。
キリスト教徒にとって重要なのは国家ではなく個人の救済であり、それは啓示により完成する。そして、啓示は人間の実存の外、すなわち外部から突然やってくる。
タグ :佐藤 優
2011年09月29日
はじめての宗教論 右巻 ー第3章 プネウマとプシュケーー
第3章 プネウマとプシュケー
<目次>
霊と魂を区別する
「神の霊」はどう表象されるか
二分的思考法と主客未分化の思考
ソクラテスが死を恐れなかった理由
キリスト教と霊魂不滅説
実念論と唯名論
中世哲学の最新成果
オッカムの剃刀
アベラールとエロイーズ
唯名論とはなんだったのか
普遍論争の新しい図式
「唯名論vs実念論」の背景
唯物論の対立概念とは?
<要約>
「見える世界」「見えない世界」を繋ぎなおすために宗教を論じる必要がある。
その繋ぎなおす装置として「プネウマ(霊)」と「プシュケー(魂)」の区別は大切である。プネウマはもともと息・息吹き・気の意味であり、あらゆる命の原理である。
一方プシュケーは個性である。プネウマのないプシュケーは存在しない。
ソクラテスは毒杯をあおって死んだが、死ぬことでプシュケーが解放されると信じ、死を恐れなかった。
中世哲学の最大の論争に「普遍論争」がある。
普遍universalia (類と種) は自然的実在であるか, それとも知性の構成物にすぎないかをめぐって行われた。
一般的に唯名論、実念論、概念論、にそれぞれ立場が分かれるとされる。
唯名論 なしとイチゴとメロンを一緒にくくれるのかを考える。ナシは木になるし、イチゴは草だ。メロンはむしろきゅうりと一緒だが、とりあえず関係があるという形で暫定的に「くだもの」という一つの名称にまとめる。
実念論 まず果物がある。そのなかにメロン、イチゴといった個物がある。果物自体は何かといったら人知ではわからない。しかし、確かに存在する。
このふたつの折衷案として、概念論がある。果物という概念はあるが目に見えない。実態としてあるものではない。それは概念として存在し、そこからナシやメロンイチゴが生み出される、と考える。トマス・アクィナスが有名である。
実念論、概念論、唯名論を「個別の前」「個別の中」「個別の後」とするが、しかし、それは近代の視座であって、実際の中世の内在的な感覚と違っている可能性がある。
では、なぜ実念論と唯名論が出来てしまったか、というとそれは神学部と哲学部の対立にあったのではないか。神学部では「なぜそうなっているのか?」とものの本質について質問するのは神学部だけであった。
一方、哲学は現象界をどう見るかという論理学が発達した。
ラチオ(合理性)を基本にして判断すると、論理的成功性の高いほうが勝つ。だから、中世では神学部は少しづつ地歩を失っていった。
参照(ネットで百科より):
普遍論争 ふへんろんそう Universalienstreit[ドイツ]
普遍universalia (類と種) は自然的実在であるか, それとも知性の構成物にすぎないかをめぐって行われた中世哲学最大の論争。 前者の主張を実念論(欧語は実在論と同一だが近代の観念論に対するそれと区別して概念実在論, 略して実念論と称することが多い),後者の主張を唯名論と呼んでいる。 この問題はプラトンとアリストテレスのイデア理解の相違にさかのぼるが, 古代哲学においては一般に認識は対象を離れてはなく, 論理学が形而上学から独立することがなかった。 5 世紀末~ 6 世紀初めのローマの哲学者ボエティウスによって初めて論争の種がまかれた。 初期スコラ学では実念論が優勢であったが, 後期には唯名論が明確となって近代的思考が用意されたという経過をとっている。
論争は同時に神学にもおよんだ。 11 世紀末のカンプレの司教オドOdoは原罪遺伝説を擁護し, アダムは多数の個の実体的統一であるから, アダムの子らはみな同一実体で,性質のみが異なると主張した。 他方,オドと同時代でアベラールの師でもあったロスケリヌスRoscellinusは, 実在するものは個物のみで,普遍はたんなる〈音声 vox〉にすぎないと考えて, 三位一体ではなく三神論を主張するに至った。 アベラールはこの極端な唯名論をやや緩和して, 普遍とは有意味な語たる〈ことば sermo〉ないし〈名辞 nomen〉がさし示す意味であり, 〈個物の一般的な漠然たる印象〉がこれに対応すると考えた。 その後シャルトル学派やサン・ビクトール学派では, 比較や抽象という知性の作用によって普遍概念が形成されることがみとめられた。
13 世紀のトマス・アクイナスはアラビアの哲学者イブン・シーナー (アビセンナ) の説をとり入れ, 普遍は神的には〈ものの前に ante rem〉, 自然的には〈もののうちに in re〉,知性の抽象によって〈ものの後に post rem〉あると考えた。 したがって普遍は知性の所産であるとともに実在に対応するものとされる。 これは〈穏やかな実念論〉と呼ばれる。 14 世紀に入ると,個物は普遍的本質によって規定しつくされない独自の存在であるとする個体主義が登場した。 トマスは,神は人間の知りうる現実以外のものをつくりうるとして創造の不可知の可能性をみとめ, これを神の全能と摂理に帰したので, その限りで普遍が事物に先立ち神の知性のうちにあることを主張したが, 後期スコラ学者は神を個的な無限者とみて, 普遍概念とその必然性を神のうちにおくことをしなかった。 この精神はルターにも影響している。
オッカムは〈意味 significatio〉と〈代置 suppositio〉とを区別する。 例えば〈ひとは死ぬ〉という命題において, 〈ひと〉は一定の人を表示する意味ある語であるが, これは〈ひと〉という概念 (概念名辞 terminus conceptus) と解して初めて命題のうちにおかれ, 個々人を記号的に代置し指示すると解されるのである。 これによりオッカムは唯名論を論理学的に基礎づけ, かつ事物それ自体の認識は直観によることを主張して, 形而上学的独断を排する経験主義の立場を明らかにした。
泉 治典
タグ :佐藤 優