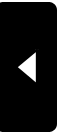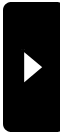2011年09月29日
はじめての宗教論 右巻 ー第3章 プネウマとプシュケーー
第3章 プネウマとプシュケー
<目次>
霊と魂を区別する
「神の霊」はどう表象されるか
二分的思考法と主客未分化の思考
ソクラテスが死を恐れなかった理由
キリスト教と霊魂不滅説
実念論と唯名論
中世哲学の最新成果
オッカムの剃刀
アベラールとエロイーズ
唯名論とはなんだったのか
普遍論争の新しい図式
「唯名論vs実念論」の背景
唯物論の対立概念とは?
<要約>
「見える世界」「見えない世界」を繋ぎなおすために宗教を論じる必要がある。
その繋ぎなおす装置として「プネウマ(霊)」と「プシュケー(魂)」の区別は大切である。プネウマはもともと息・息吹き・気の意味であり、あらゆる命の原理である。
一方プシュケーは個性である。プネウマのないプシュケーは存在しない。
ソクラテスは毒杯をあおって死んだが、死ぬことでプシュケーが解放されると信じ、死を恐れなかった。
中世哲学の最大の論争に「普遍論争」がある。
普遍universalia (類と種) は自然的実在であるか, それとも知性の構成物にすぎないかをめぐって行われた。
一般的に唯名論、実念論、概念論、にそれぞれ立場が分かれるとされる。
唯名論 なしとイチゴとメロンを一緒にくくれるのかを考える。ナシは木になるし、イチゴは草だ。メロンはむしろきゅうりと一緒だが、とりあえず関係があるという形で暫定的に「くだもの」という一つの名称にまとめる。
実念論 まず果物がある。そのなかにメロン、イチゴといった個物がある。果物自体は何かといったら人知ではわからない。しかし、確かに存在する。
このふたつの折衷案として、概念論がある。果物という概念はあるが目に見えない。実態としてあるものではない。それは概念として存在し、そこからナシやメロンイチゴが生み出される、と考える。トマス・アクィナスが有名である。
実念論、概念論、唯名論を「個別の前」「個別の中」「個別の後」とするが、しかし、それは近代の視座であって、実際の中世の内在的な感覚と違っている可能性がある。
では、なぜ実念論と唯名論が出来てしまったか、というとそれは神学部と哲学部の対立にあったのではないか。神学部では「なぜそうなっているのか?」とものの本質について質問するのは神学部だけであった。
一方、哲学は現象界をどう見るかという論理学が発達した。
ラチオ(合理性)を基本にして判断すると、論理的成功性の高いほうが勝つ。だから、中世では神学部は少しづつ地歩を失っていった。
参照(ネットで百科より):
普遍論争 ふへんろんそう Universalienstreit[ドイツ]
普遍universalia (類と種) は自然的実在であるか, それとも知性の構成物にすぎないかをめぐって行われた中世哲学最大の論争。 前者の主張を実念論(欧語は実在論と同一だが近代の観念論に対するそれと区別して概念実在論, 略して実念論と称することが多い),後者の主張を唯名論と呼んでいる。 この問題はプラトンとアリストテレスのイデア理解の相違にさかのぼるが, 古代哲学においては一般に認識は対象を離れてはなく, 論理学が形而上学から独立することがなかった。 5 世紀末~ 6 世紀初めのローマの哲学者ボエティウスによって初めて論争の種がまかれた。 初期スコラ学では実念論が優勢であったが, 後期には唯名論が明確となって近代的思考が用意されたという経過をとっている。
論争は同時に神学にもおよんだ。 11 世紀末のカンプレの司教オドOdoは原罪遺伝説を擁護し, アダムは多数の個の実体的統一であるから, アダムの子らはみな同一実体で,性質のみが異なると主張した。 他方,オドと同時代でアベラールの師でもあったロスケリヌスRoscellinusは, 実在するものは個物のみで,普遍はたんなる〈音声 vox〉にすぎないと考えて, 三位一体ではなく三神論を主張するに至った。 アベラールはこの極端な唯名論をやや緩和して, 普遍とは有意味な語たる〈ことば sermo〉ないし〈名辞 nomen〉がさし示す意味であり, 〈個物の一般的な漠然たる印象〉がこれに対応すると考えた。 その後シャルトル学派やサン・ビクトール学派では, 比較や抽象という知性の作用によって普遍概念が形成されることがみとめられた。
13 世紀のトマス・アクイナスはアラビアの哲学者イブン・シーナー (アビセンナ) の説をとり入れ, 普遍は神的には〈ものの前に ante rem〉, 自然的には〈もののうちに in re〉,知性の抽象によって〈ものの後に post rem〉あると考えた。 したがって普遍は知性の所産であるとともに実在に対応するものとされる。 これは〈穏やかな実念論〉と呼ばれる。 14 世紀に入ると,個物は普遍的本質によって規定しつくされない独自の存在であるとする個体主義が登場した。 トマスは,神は人間の知りうる現実以外のものをつくりうるとして創造の不可知の可能性をみとめ, これを神の全能と摂理に帰したので, その限りで普遍が事物に先立ち神の知性のうちにあることを主張したが, 後期スコラ学者は神を個的な無限者とみて, 普遍概念とその必然性を神のうちにおくことをしなかった。 この精神はルターにも影響している。
オッカムは〈意味 significatio〉と〈代置 suppositio〉とを区別する。 例えば〈ひとは死ぬ〉という命題において, 〈ひと〉は一定の人を表示する意味ある語であるが, これは〈ひと〉という概念 (概念名辞 terminus conceptus) と解して初めて命題のうちにおかれ, 個々人を記号的に代置し指示すると解されるのである。 これによりオッカムは唯名論を論理学的に基礎づけ, かつ事物それ自体の認識は直観によることを主張して, 形而上学的独断を排する経験主義の立場を明らかにした。
泉 治典
タグ :佐藤 優
ヨン様やヅカにハマる人、ハマらない人。
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その2-
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その1-
はじめての宗教論 左巻 -第2章 宗教とナショナリズム-
はじめての宗教論 左巻-第1章 近代とキリスト教-
はじめての宗教論 左巻 -序章-
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その2-
はじめての宗教論 左巻 -第3章 神学入門1 その1-
はじめての宗教論 左巻 -第2章 宗教とナショナリズム-
はじめての宗教論 左巻-第1章 近代とキリスト教-
はじめての宗教論 左巻 -序章-
Posted by キミドリ at 07:00│Comments(0)
│10分くらいで読んだ気になれる、かも。